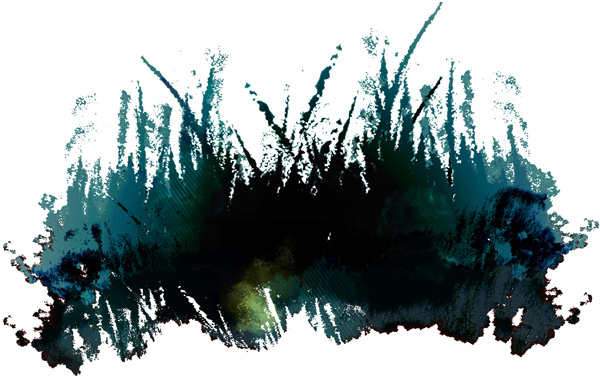
普段は静寂に包まれる森に荒々しい物音が響き渡る。 騎士や傭兵達の剣戟の音や討伐対象である獣達の咆哮。 森中に濃厚な戦闘の気配が漂う中、シリスも群がるかのように襲い掛かる翡翠の体毛に覆われたモンスター達を双剣を振るい屠っていく。 後衛を受け持つテッドは素早く矢を放ちシリスを援護し、接近を許したものには素早く短刀を振るい始末をつける。 夥しい獣達の応酬に逸れてしまった仲間達のことを考える暇も無く剣を振るう。 シリスにとっての幸運はとやはりテッドと行動を共にできたことだろう。 彼とは馬が合うという以上にしっくりと合う。 初対面とはとても思い難い、おかしいほどの一致だった。 不思議な一体感に酩酊するかのように自然と剣が動き、目を逸らした瞬間に耳のすぐ近くを縫うようかの軌道で矢が空気を唸らせ飛び交う。 ザンッ。 最後の一匹に一太刀を浴びせそのまま血と脂を振るい落とし鞘に収める。 はぁ、と荒い呼吸を落ち着かせようと身を屈めながら大きく呼吸するシリスの背後に、こちらも肩で息を吐くテッドがゆっくりと駆け寄りながら問う。 「回復しようか?」 詠唱準備に入ったのかテッドの左手が淡く水色の光を放つのを見つめ、シリスはゆるりと首を振った。 「いや、テッドの紋章はまだ温存しておいてくれ」 ここら一帯のモンスターはなんとか一掃したとは言え、未だ至る所で戦闘の気配は続きつつあり、辺りをうろつく獣達の気配も肌に感じる。 いつまた戦闘に陥るか分からない中、後衛にて素早く発動できる紋章を使ってしまうのは頂けない。もちろんすでに残量が心もとない薬草の類もここで使ってしまうのは忍びない。 「俺の紋章で回復しよう」 多少ラグが生じてしまう自分の流水の紋章を使うことが一番だ。そうシリスは結論付け、未だ馴染みきっていない紋章を発動させた。 「しっかし、数が多いな。」 小休止、と大木に背を預け座り込んだ二人は水筒の水を啜りながら会話を続ける。 「まだ辺りにはヤツらがうろついてる気配もするし、ここまで長丁場になるとはな」 テッドのため息交じりの言葉にシリスも静かに頷き、思案するように青い瞳を細めた。 「事前の情報とも少し違う。ここまで凶暴とも聞いてなかったし、その上知恵もあるようだ」 「ああ。見事に分散させられたな」 「一度撤退してみた方が良いかもしれない。」 「・・・、そうだな。二人だけでここから進んで巣を見つけたとしても、俺達だけじゃどうしようもないしな」 「・・・。」 しかし・・・、 シリスは心にポツリと浮かんだ言葉を飲み込んで眼前に広がる緑を睨んだ。木の幹の合間を縫い、その奥、暗闇の緑を。 しかし、事はそう上手く運ぶだろうか。 奴等はシリスたちを同士から引き離した後、まるで奥へ奥へと誘い込むかのように襲い掛かってくる。ほんの僅かな違和感さえも感じさせぬように、まるで狡猾に。 シリスは無意識に、それを悟っていたのかもしれなかった。 お互い息が整った頃、二人は目配せだけで立ち上がり先ほどの話の通り一旦帰路を目指すこととした。 手間を省くためなるべく気配を絶ち、魔物たちを避けながら森の出口を求めて歩く。 半分ほどの道を戻っただろうか、その時シリスは目前に見慣れない光の反射を見つけ足を止めた。 後方に意識を向けていたテッドに合図を送り気配を絶ちながらそちらを草の陰から慎重に探る。 「なんだ?」 「分からない・・・けど森の中にあんな物が転がっているなんてことは・・・」 辺りに気配が無い事を確認した後、シリスは地面に数個ごろごろと転がっているものを見下ろした。 それは緑の水晶だった。 しかしこの辺りで水晶や鉱石の類が採掘されたなどという話は聞いた事はないし、そしてこの大きさだ。 今まで気づかないはずが無い。 これは忽然と現れたものだった。 それは人一人でも入り込んでしまいそうなほど巨大な水晶の塊。 カッティングでも施されているように滑らかな表面で光を反射する緑の水晶はまるで鬱蒼としたこの森を写し取ったかのように、中心に行くほどに曇りその内面に光の屈折を隠してしまっていた。 罠の類もなさそうだとシリスは転がる一つの水晶、その一際大きなものに近づき膝を付いてじっくりと見下ろした。 「・・・・・。」 深く、くすんでいく水晶の中に何かが見える。 「・・・っ」 目を凝らして見えたものに、シリスは鋭く空気を飲んだ。 「シリス・・・?」 後ろに立ったままでシリスの様子に怪訝なものを感じたテッドの問いかけに答える余裕など微塵も無かった。いや、その声さえも聞こえてはいなかったのかもしれない。 どうして、と音も無く唇が動く。 そして名前を呼ぶ。 人ほどもある巨大な水晶。翡翠かヴェルディグリかそれとももっと別の何色か、その深い色の中には男が一人納まっていた。 苦悶の色など浮かべることなくただ無表情に屈強な男が死んだように、眠るように、ただ静かに瞼を下ろしてそこにいる。 「グ、レン・・団・・長・・・・・」 乾いた唇から搾り出されたその名前は、草木を揺らすことも無くゆっくりと沈んだ。 テッドはそのシリスの背中と傍らの水晶を静かな瞳で見下ろしていた。 20120427 20140417up ← → novel |