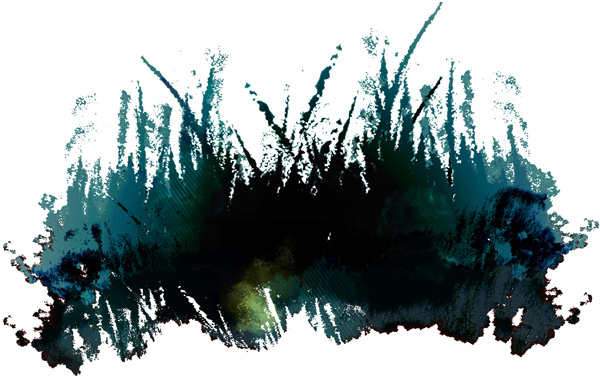
ざん。と微かに漣の音が聞こえた。 閉じた瞼の裏には透き通るような青が広がり、呼吸するかのようにゆったりと濃淡が揺れる。 それに呼応するかのように寄せては引き、引いては寄せる波の音が鈍く残響する。 泡の弾ける音が遠くで無数に響き、風に煽られる水面がざんざんと音を立てる。 深い海の底で、それを見上げる瞳があった。 青い陰に沈む中にほんの少し青光が差し込む。 ゆらゆらと海草のように揺れ、視界を遮る金茶の髪が反射してちらちら光を鈍く孕んだ。 瞼をそっと下ろせば何も見えなくなる。 浮遊するような中、青い闇の中に居る。頭に響く残響は遠ざかり近づき、何度もそれを繰り返しながらゆっくりとその音は消えていった。 薄汚れたクリーム色の壁が見えた。 いまだ霞んでいる視界にうめきながら寝返りを打った。 すでに見慣れた天井を見上げた後にゆっくりと身体を起こす。 締め切れて居なかったカーテンの隙間から、町並みに微かに海の青が見えた。 シリスは顔を覆うやや長めの前髪を掻き分けた後、ぐっと身体を伸ばす。 白いシーツから逃げ出した後、裸足のまま洗面台に向かった。 硬い蛇口を回すと勢い良く冷水が流れ出す。 しばらく手をつけその冷たさを馴染まそうとする。しかし毎朝のことだというのにシリスはこの冷たさにいつまで経っても慣れることがない。 顔をこわばらせながら無理やり水に顔をつけると、さすがにぼやけたままの頭もはっきりとしてくる。 一仕事終わった、とばかりに用意してあったタオルで水を拭いつつ顔を上げると、その先には磨かれた鏡に映る男の顔がある。 微かに水気を帯びた重そうな前髪の下には円い青い瞳が猫のようにひっそりとこちらを見つめていた。 シャープな輪郭を支えるには少し頼りなさげな白い首筋に、不精に伸ばされた毛先がかかっている。 二十代半ばに差し掛かると言うにはシリス自身にもどこか物足りなさを感じさせる面差しである。 じっ、と鏡の中の男と目線を交わした後シリスは背を向け今度はクローゼットへ向かう。 先日クリーニングから帰ってきたばかりでいまだ袋に包まれたままの騎士団服を取り出す。 慎重な手つきで袋にダメージを与えないように団服を出した後、まずはゆったりとした寝巻きのズボンから丈夫な生地のそれに履き替える。 インナーの黒いタートルネックのシャツを着込んだあと、上着だけは椅子の背もたれに掛けたまま、一度部屋を出る準備を始めた。 朝早いとは言え、騎士団寮の食堂は微かな騒音に満ちていた。 様々なローテーションの元働く騎士が居り、それをサポートするための一角である食堂に物音が響かないなどそれこそ真夜中ぐらいのことだろう。 シリスは行き交う同僚たちに挨拶を返しながらカウンターへ向かう。 「やあシリスおはよう」 カウンターの中からフンギが気さくな笑顔で声を掛けてくる。 「おはよう」 「今日も早いね、今日は遅番だったんじゃないのかい?」 「目が覚めちゃってね」 肩をすくめ笑い混じりに答えるとフンギは困ったものを見るかのように苦笑いして返してくる。 「未だに小間使い時代のクセが抜けてないんじゃないかい?」 「そうみたいだ」 幼い頃フィンガーフートに拾われたシリスは年頃の近い子息の友人兼側仕えとして勤めてきたが、海上騎士団入団と同時にフィンガーフート家を離れこの騎士団寮に住み着いた。 海兵学校卒業と同時に寮を出て屋敷に戻った子息スノウとは別れる事となったが、今では垣根のない友人として接している。 後見を務めてもらっているとは言え、今やフィンガーフートの使用人としての生活を送ってはいないはずなのだが、幼い頃から今まで、それこそ二十年近くにも及ぶ習慣であったためシリスはどうもしがらみの無い生活に順応し損ねているようだった。 数年前ならば今頃、とっくに起きだしたシリスは嵐のような慌ただしさの厨房で雑用に追われていただろう。 それに比べて今このときのなんて穏やかなことかとシリスはため息をつく。 「寝直す気にもなれないからね、とりあえずさっさと朝食を摂ってしまおうと思って」 「早すぎる朝食だろ」 からかうように笑ったフンギはシリスにしばし待つように言った後、調理を始めた様子だった。 カウンターに背を預け向こうの窓を見上げると、その外にはまだ微かに白んだ空が広がっていた。 これといってすることが無い。 それが目下シリスを悩ませていることだった。 幼い頃から奔放なスノウに付き従っていたシリスに自由はあまりに乏しく、何かに没頭すると言うことは無かったのだ。 あえて言うならば、やはり剣を振るうことだろうか。しかしそれは仕事の一部で鍛錬すべきことであり、そこにやりがいは見つけることは出来ても楽しみを見出すものとは違ったものだとシリスは考えていた。 とりあえず部屋にいる気にはなれない。 シリスはそう思い当たり、私服の上着に腕を通した。 青を基調とした団服とは違い、黒とワインの様な渋みのある赤に染められている。 私服とは言え剣士のシリスが選んだそれは丈夫な造りをされている。 騎士足るもの己の命を預けた剣を手放してならないという教えに従い、腰に巻いたベルトには使い込まれた双剣が差し込まれている。 髪を黒いヘアゴムで首の後ろで縛った後に、もう一つ、頭に巻きつけようとして気が付いた。 いつも頭に巻いていた赤い布はこの前の任務時に解れてしまった為、繕おうと思っていたままだった。 シリスは決まり悪げに動かしかけた手を下ろした後に頬を掻く。 相変わらず自分は習慣と言うものに縛れら過ぎてしまうのだ。 自覚は無いのだがもしかして自分でも呆れてしまうほどの石頭だったのではないか、そう考えてしまう。 まあ、いい。 シリスは換気のために開けていた窓を閉め簡単に戸締りを終えた後に部屋を出た。 フンギの話し方ってどんなんでしょうか。 騎士団のなんたるかも良く分かってないんですが。 まあいいよ、捏造捏造♪ この後もどんどん捏造が進みます。 20120427 → novel |